「遊び」の余白と、補助線
今日は土曜日、語学授業はお休みです。
午前中は、「ACP(アクティブ・チャイルド・プログラム)」という、遊びを通した子どもの教育プログラムに関する講座を受けました。
日本だけでなく世界共通で、子どもたちの「遊び」の時間が減っている。それによって、体力や運動能力(特に「投げる」といった複雑な動き)が低下するだけでなく、コミュニケーション能力や我慢する力まで失われている。
「遊びの可能性」。大人が指導しなくても、子どもたちが自発的に遊び出すような「場・仕掛け」や、答えを教えすぎない「余白」が、彼らの創造性を引き出すのだと学びました。
「事実」よりも強い、「印象」という言葉の魔力
午後は、福島の原子力発電所に関して学習する機会がありました。 詳細は記せませんが、そこで強く印象に残ったのは、「科学」という事実よりも、「政治」という印象の方が、世の中を動かす力が強いということです。
これは、以前の福島県オリエンテーションでも伺った話ですが、事実はどうあれ、一度ついた「印象」が世界の行動原理になってしまう。だからこそ、メディアがいかに、そしてどのように物事を伝えるかが、非常に重要になってくるのだと改めて実感しました。
私が発信する、言葉の責任
私自身も、ケニアに派遣された後、情報発信を続けていくつもりです。 しかし、今日の学びを通して、その言葉の責任の重さを改めて考えさせられました。こちらが意図しない形で言葉は伝わり、一人歩きしてしまう可能性がある。そのことを常に念頭に置き、一つ一つの発信に責任を持たなければならないと、強く思いました。
「遊び」における余白の大切さと、「言葉」が持つ責任の重さ。 一見すると全く違う二つの学びが、どこか「伝える」ということの本質で繋がっているような、そんな深い気づきのある一日でした。

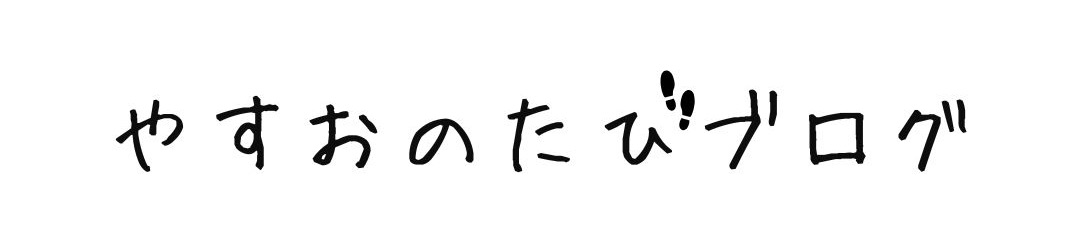

コメント