新しい週と、ラジオ体操第ニ
早くも3週間が経過し、新たな一週間が始まりました。
時の流れの速さに、少し焦りさえ覚えます。
今朝は4時半に起床し、英語の予習から一日をスタート。食べる量を増やしたおかげか、この生活リズムに体が馴染んできたのか、心なしか体の調子が良い気がします。
今日から朝のラジオ体操が「第二」になりました。高校の体育の授業を思い出す、少しだけ難易度の上がった動き。毎朝の集いでのこうした小さな変化や儀式が、私たちの団結力を高めてくれているように感じます。集団行動における「儀式」の重要性や意味に思いを馳せながら語学の授業に向かいます。
もどかしさと、向き合う
今日の語学の授業は、スマートフォンについてのディスカッションから始まりました。
まだまだ語彙が足りず、言いたいことが言えないもどかしさを感じてばかりです。でも、この悔しさをバネに、次に同じテーマが出た時は必ずもっと話せるように、復習を徹底しようと思います。
早速、ジャーナルで今日うまく表現できなかったものを表現し直してみます。
手話という、豊かで新しい言語
夜は、言語聴覚士の資格を持つ同期などによる「手話」の自主講座がありました。
本当に素晴らしい講座でした。
ジェスチャーや表情を大切にしている方ならではの、豊かな感情表現でぐいぐいと私たちを引き込み、会場を盛り上げる技術は、プロフェッショナルでした。
ひとえに聴覚障害と言っても様々な種類があること。そして、音が聞こえづらい人は、言葉の習得が遅れることで、感情の表現も苦手になる場合があるということ。初めて知ることばかりで、衝撃を受けました。
そして、実際に手話を少しだけ学び、その表現の豊かさに心を奪われました。一つ一つの動きが、日本人の物事の捉え方や考え方を映し出しているようで、非常に興味深いです。
私の任地であるケニアでは、手話が公用語の一つとして認められています。
いつかケニアの手話を学ぶことで、彼らの世界の見方に少しでも触れることができたら、とても面白いはずです。ぜひタイミングをみて、学んでみようと思います。


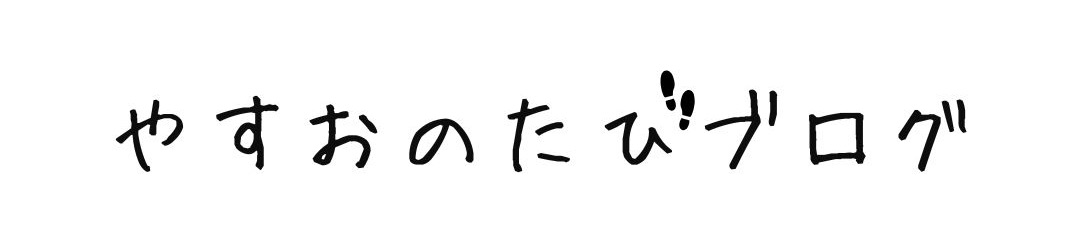

コメント