熱意に触れた、戸馳島での一日
今日は一日、イノPの活動で熊本林業大学校の戸馳島視察に同行させていただきました。午前は座学、午後はフィールドワークです。稲葉さんの講義は3回目ですが、参加者に合わせて毎回内容がカスタマイズされており、特に今回は林業の未来を担う方々の熱意も相まって、非常に濃密な時間となりました。
森の静かな悲鳴と、テクノロジーの可能性
午前中の座学で突きつけられたのは、日本の林業が抱える深刻な鹿被害の現実です。鹿は好きな植物から食べ始め、それが尽きるとあらゆるものを食べ尽くします。わずか15年でその数は10倍に膨れ上がり、新芽はことごとく食べられ、山は保水力を失い、砂利だらけの土地へと変わっていきます。
150万円以上かけて設置した防護ネットも下から破られ、大切に育てた苗木は、まるで盆栽のように無残に食い荒らされてしまう。この静かで着実に進行する災害に対し、分業化された現場ではどこか「他人事」になりがちで、対策の責任の所在さえ曖昧だという現実に、構造的な問題の根深さを感じます。
そしてもう一つ、林業はまだまだアナログな世界だということです。特に山奥での通信環境の欠如は、万が一の事故や緊急時の対応に直結する深刻な問題です。
そこに光を差すのが、スターリンクのような衛星技術です。衛星の数が飛躍的に増え、今や山奥でも日常的にインターネットが使えるようになれば、安全性は格段に向上します。こうしたテクノロジーの活用の幅はまだまだあるはずで、その導入を主導していくのが、私たち若い世代の役割なのだと強く感じました。

命と向き合い、未来をデザインする
午後のフィールドワークでは、実際に罠や解体施設を見学させていただきました。そこで語られたのは、命との向き合い方、そして未来のライフスタイルの可能性です。
例えば、アニマルウェルフェア(動物福祉)の話。ストレスを与えずに止め刺しをすることで死後硬直が遅れ、肉のpH値が理想的に変化する。結果として、それは驚くほど「美味しい肉」になるのです。命をいただくことへの敬意が、そのまま価値に直結するという事実は、私たちが学ぶべき深い哲学を教えてくれます。
また、林業を軸としながら、新しいビジネスを生み出す可能性についても話が及びました。「素材生産」という安定した仕事と、「造林」という比較的休みを取りやすい仕事。この二つの特性を活かし、空いた時間で自分の興味を追求する。カブトムシの養殖のような、一見すると林業とは関係のない分野にも、未来のライフスタイルを豊かにするヒントが隠されています。
林業は、単なる仕事ではなく「生き方をデザインするための一つの選択肢」なのだと、改めて感じました。

教えることは、教えられること
視察の合間には、いつも通り青年海外協力隊について話す時間をいただきました。今回は特に質問が多く、休憩時間にも熱心に話を聞きに来てくれる方が多かったのが印象的です。林業大学校には、自らの人生を深く見つめ、目的意識を持って集まっている人が多いのかもしれません。
夜は、1週間ぶりのサッカーへ行きました。暑さのせいか、子供たちの集中力がなかなか続かないようでした。「自分ならこうするのに」という考えが何度も頭をよぎりますが、その度に、それは何の意味もないことなのだと思い知らされます。
相手の立場や気持ちを汲み取れなければ、教えるという行為は成立しません。それは、林業の現場が抱える問題も、新しいライフスタイルを提案することも、そして海外での活動も、全てに共通することでしょう。
教えることを通して、私自身が一番大切なことを教えられているのだと、汗を流しながら考えていました。

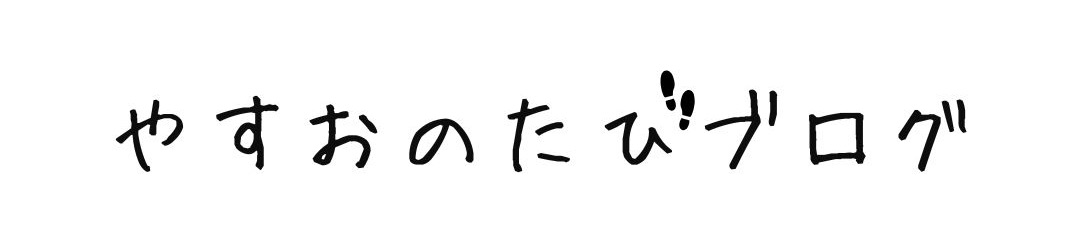

コメント