今日は、先日お会いしたNHKの元ディレクターの方に、5年前に起きた球磨川氾濫の被災地を案内していただきました。
球磨川沿いに入ると食事処が少ないということで、まずは八代で昼食を取ることに。熊本でよく食べられているという、ちゃんぽんのお店を目指します。お盆ということもあり、調べたお店は2軒続けて営業しておらず、少し諦めかけながら向かった3軒目で、ようやく席に着くことができました。昔ながらの雰囲気と、店員さんの温かい接客が素敵な、良いお店でした。
川の美しさと災害の爪痕
そして、いよいよ球磨川流域へ。一つ目の目的地である坂本村に向かう道中、その川の広さと、エメラルドグリーンに輝く美しさに目を奪われます。しかし同時に、嵩上げの工事の多さが、この先に待つ現実を静かに物語っていました。
坂本村では、案内してくださった方が仕事部屋として購入されたという家で、元々あった家具の運び出しをお手伝い。その集落は、東京の喧騒とは最も遠い場所にあるような、深い静けさに包まれていました。
その後、人吉市へ向かう道中で、私は言葉を失いました。 5年という歳月が経った今もなお、土砂に埋もれたままの家、無残に壊れた大きな橋、使われなくなった線路。そして、不自然なほど綺麗に更地化された川沿いの土地と、ジャッキで高く嵩上げされている最中の家々。その傷跡は、あまりに生々しく、鮮明でした。

「想定外」を想定する力
案内していただきながら、当時の映像も見せていただきました。あんなにも穏やかに見えた川の水位が、何十倍もの高さまで膨れ上がり、家を流し、橋を壊していく。それは、私が当時ニュースで見ていた「他人事」の災害ではなく、もはや地球最後の日にさえ見える、現実離れした光景でした。その映像を通して、この災害に、初めて確かな「温度」を感じた気がします。
高く嵩上げされている家を見ても、案内の方は「それでもまだ足りないだろう」とおっしゃいます。「想定外」は、必ずまた起きる。過去に何が起きたかではなく、これから起こりうる、より深刻な事態を見据えなければならないのだ、と。
今回この場所に案内していただいた背景には、「ケニアでの活動に、何か役立つかもしれない」というお心遣いがありました。昨年、ケニアでも大洪水が起きています。災害は、いつ、どこで起きてもおかしくない。その時、最も重要になるのは、痛い目を見る前に、いかにして「当事者意識」を持てるか、ということなのだと感じます。道中、ふと遭遇した三頭の鹿。一見すると愛らしいその存在も、下草を食べ尽くし、土砂災害の一因となるという「知識」がなければ、その本質は見えてこない。もっと、学ばなければなりません。


球磨焼酎が教えてくれた哲学
さて、人吉では、水害の記憶に触れながらも、もう一つの目的がありました。今度、案内してくださった元ディレクターの方が講演で話すという「球磨焼酎」についての調査です。立ち寄った酒屋の店主が、その奥深い世界を語ってくれました。
時代と共に、飲みやすい減圧蒸留が主流になり、樽やスパイスで風味付けをするなど、焼酎もまた変化してきたこと。しかし、と彼は言います。「酒好きが最後に還ってくるのは、『極楽』や『球磨の泉』のような、昔ながらの常圧蒸留が持つ、あの『癖』なんだ」と。
そして、こう続けました。「最近の酒は、人に合わせてくれる。でも、本当は違う。酒がこちらに合わせるんじゃなく、人が、その酒の個性を理解しに、迎えにいくんだよ」。
その言葉に、私はハッとさせられました。それは、余市のウイスキー造りにも通じる、作り手の哲学と、飲み手の覚悟が交差する、なんと面白い世界でしょう。ただ消費するのではなく、その背景にある物語や想いまで含めて味わう。もっと、各地の酒を知りたい。その味も、作り手の顔も。
災害という自然の猛威と、焼酎という文化の深淵。その両極に触れ、自分の無知を痛感すると共に、知ること、学ぶことへの渇望を、改めて強く感じた一日でした。


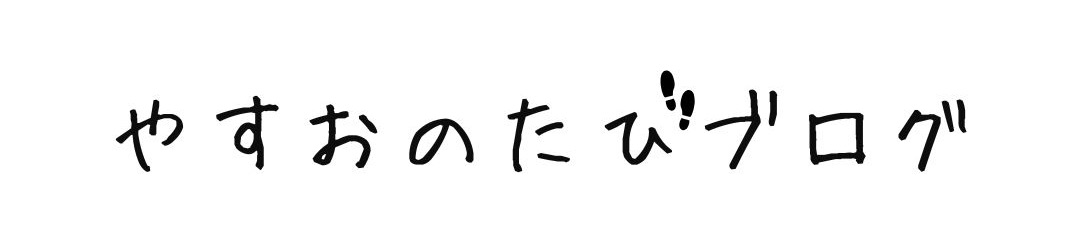

コメント