お盆休み最終日の今日、私は一日をかけて、この研修の最終報告資料の作成に没頭していました。活動期間も、残り2週間。終わりが見えてきたからこそ、この1ヶ月半の日々がいかに濃密で、多くの出来事に満ちていたかを、改めて思い出します。資料をまとめる手は、大方終わりました。
残りの時間は、この場所での活動を心から楽しみ、そして頑張り抜こうと思います。
そして、今日という日が、日本にとって非常に重要な意味を持つ一日であることを、静かに噛み締めていました。
「記憶」から「歴史」へ。世代交代がもたらす、冷静な分析の好機
8月15日。
ポツダム宣言を受諾し、太平洋戦争が終結してから、80年。
「戦没者を追悼し、平和を祈念する日」です。
しかし、80年が経ち、世界中で分断の亀裂が深まる今、「祈念する」だけでは、もはや平和は維持できないのではないか。私は、そんな強い危機感を抱いています。
当時20歳だった方も、今や100歳。戦争を直接知る世代が、私たちの社会から少しずつ姿を消していく。それは、貴重な一次情報である「記憶」を失う、計り知れない損失です。
しかし、同時にそれは、私たちがこの悲劇を、感情的な記憶から、客観的な分析対象としての「歴史」へと昇華させるべき時代の到来をも意味しているのだと思います。
『日本のいちばん長い日』で描かれたように、天皇の神格化、国体護持という思想、そして陸海軍の縦割り行政。これらは、特定の誰かが悪かったという個人史観で語るべきものではなく、どんな社会でも再現されうる、極めて危険な「構造的な問題」です。
だからこそ今、感情を一度脇に置き、第三者の視点で冷静に事実を認識し、分析するチャンスが、私たちには与えられています。
「何が起きたか」ではなく、「なぜ起きたか」を学ぶ
私は、日本の義務教育における歴史の授業が、退屈でなりませんでした。年号や出来事を、歌や語呂合わせで暗記する。その行為の、なんと知的生産性の低いことか。
本当に重要なのは、「何が起きたか」ではなく、「なぜ、それが起きたのか」であるはずです。どのような構造的問題があり、どのような条件下で、その悲劇は再現されうるのか。それを考え、議論することこそ、歴史の授業があるべき姿ではないでしょうか。
また「先生は中立であるべきだ」という建前の下、教員が自らの意見を語らない風潮も、私は疑問に思います。この世に、完全に中立な人間など存在しません。「事実はこうだ。私はこう考える。しかし、別の考え方もある。それを踏まえ、あなたはどう考える?」と、生徒一人ひとりに、主権者としての思考を促すこと。それこそが、教育のあるべき姿ではないかと思います。
そうでなければ、「意見を持たないこと」が、まるで正解であるかのような錯覚を生んでしまう。少なくとも、かつての私はそうでした。そして、その先にあるのは、社会への「無関心」です。
立場は、学びの中で変わっていっていい。しかし、そもそも立場を持たないことは、この不確かな世界を生きる上で、あまりに危険です。 二度とあの過ちを繰り返さないために。
80年という節目に立つ今こそ、私たちは歴史を学び直し、一人の主権者としての覚悟を、新たにすべきなのだと思います。
P.S. おすすめのコンテンツ
今日の私の思索は、あるポッドキャストから大きな影響を受けています。それが、株式会社COTENが配信する「COTEN RADIO(コテンラジオ)」です。

彼らは、まさに私が今日の記事で述べたような、年号の暗記ではない、「なぜそうなったのか」という歴史の構造的・文脈的な理解を、驚くほど面白く、深く伝えてくれます。
さらに、彼らは「歴史をデータベース化する」という、壮大で価値あるプロジェクトに取り組んでいます。その活動を支援することもまた、未来への一つの投資になるのかもしれません。歴史に、そして未来に興味があるすべての方に、心からおすすめします。


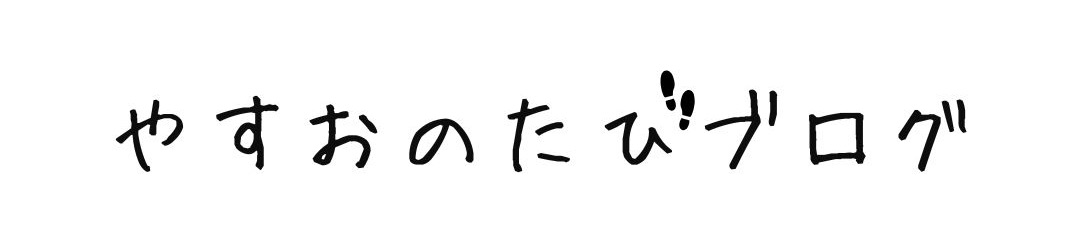

コメント