戸馳島に来て、ちょうど2ヶ月が経ちました。
お盆休みの2日目である今日は、先日からの豪雨で大きな被害を受けた八代市へ、ボランティアに向かいました。
声を上げられない地域、助けが届かない人々
行きの車中、イノPの稲葉さんが、5年前の球磨川氾濫から得た、重い教訓を話してくれました。
稲葉さんが語ったのは、支援における二つの厳しい現実です。
一つは、本当に助けが必要な「声の小さい地域」には、支援の手が届きにくいということ。メディアが取り上げるのは、救助が迅速に行き届く、ある意味で目立つ場所ばかり。しかし、本当に人手が必要な過疎地の高齢者たちは、助けを求める声を上げる手段さえ持たない。
そしてもう一つは、都市部ほど、災害後の食料やトイレの問題が深刻化するという事実でした。
その言葉を聞き、私は、まさにその「声なき声」を拾い上げることこそ、行政やメディアが果たすべき本当の役割なのではないかと感じました。
また、都市部が抱えるインフラの脆弱性は、災害の「第二波」とも言える、見過ごされがちな視点です。
ビッグサンダーマウンテンではなく、ゴミの山
「災害の終わりは、雨が止むことではない」。
現場に着き、私はその言葉の意味を、ただただ痛感させられました。場所によっては、未だに水が滝のように流れ、家の壁には、かつて水がここまで達したことを示す、生々しい茶色い線が、まるで切り取り線のように刻まれています。
私たちが手伝いに入った民家では、車が浸水で動かなくなり、家の中の廃材を災害ゴミ収集場所まで運べずにいました。その運び出しが、今日の私たちの主な作業です。
しかし、本来手伝いたかった土砂の撤去などには、ほとんど時間を割けませんでした。なぜなら、その災害ゴミを捨てるためだけに、3時間も待たなくてはならなかったからです。
見たこともないほどの、トラックの行列。その長い列の先に待っていたのは、ビッグサンダーマウンテンではなく、巨大なゴミの山でした。

思いと体力の前に、必要なこと
「なんとかしたい」という思いと、有り余る体力だけがあっても、意味がない。回収所の非効率さという、たった一つのボトルネックが、多くの善意を無駄にしてしまう。活動を円滑に進めるための「仕組み化」がなければ、個人の力はあまりに無力なのだと、思い知らされました。
車中、稲葉さんは何度も吐露していました。「なんで、こんなに熊本は災害が多いんだろう」と。 地震、台風、そして火山、、、
しかし、だからこそ、熊本は強いのだとも思います。これまでの幾多の被害の上に、学び、強くなってきたからこそ、今回の豪雨による被害は、熊本だから、最小限に抑えられた部分も多いと聞きます。
これから先、気候変動の影響で、こうした「災害」は、きっと私たちの日常にもっと頻繁に訪れるようになるでしょう。だからこそ、今日のこの経験は、私にとって未来への「抗体」を作るための、重要な機会だったと感じています。
ボランティアが直面する「仕組み」の壁。支援が届きにくい人々の存在。この現実を、ただ嘆くのではなく、当事者として体感し、自分の中に経験として蓄積する。そうして得た抗体こそが、次なる災害に立ち向かうための、そして、協力隊として困難な状況に直面した時のための、自分自身の力になる。
そう信じて、今は自分にできることを、一つひとつやっていこうと思います。


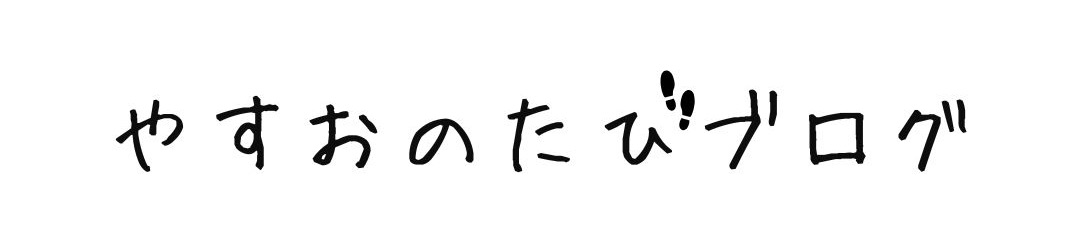

コメント