今日から三日間、お盆休み。
来るべき対話の場「車座」や、最終報告に向けた準備を進める、貴重な時間です。
まずは、クラフトジンジャーエールを作るための材料を求め、上天草さんぱーるへと電動自転車を走らせました。
スピードの裏表と、道草の価値
しかし、最初の坂道で、無情にも電動自転車の充電が切れました。そこから先は、ただの少し重い自転車。目的地までの15キロを、自らの脚力だけで進むことになります。
車なら、あっという間に目的地に着くでしょう。自転車は、遅い。でも、その遅さのおかげで、私はこれまで見過ごしていた風景を、初めて自分の画角に収めることができました。気になる脇道にふらりと立ち寄り、道草を楽しむ余裕が生まれる。

ふと、二つの言葉を思い出しました。 一つは、「賢い人は早く目的地に辿り着ける。愚か者は道草を楽しむことができる」。 そしてもう一つは、「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」。
スピードには、必ず裏表がある。どちらが良い悪いという話ではなく、人生の、あるいはプロジェクトのどの局面で、振り子をどちらに振るのか。その使い分けこそが、本質なのかもしれません。そんなことを考えながら汗を流した後は、スパタラソ天草のサウナで、思考と身体をじっくりと「ととのえ」ました。


100年前の港が、未来を指し示していた
帰り道、そういえば一度も訪れたことがなかった、世界遺産・三角西港へ。 ここは、「明治日本の産業革命遺産」の構成資産として、100年以上前の港が、ほぼ完全な形で残る、日本で唯一の場所だそうです。

設計は、オランダ人技師ムルドル。しかし、その施工を担ったのは、天草の熟練の石工職人をはじめとする、日本の技術者たちでした。西洋の最先端の設計思想と、日本の伝統的な職人技。その見事なシナジーが、100年後の今もなお、色褪せることのない「遺産」として、私たちの目の前に存在している。
この光景に、私は、青年海外協力隊が目指すべき理想の姿を見た気がしました。 外から来た人間が、ただ新しい技術を押し付けるのではない。その土地に根付く人々の生き方、文化、そして「強み」を深くリスペクトし、その上で、外の知識や技術を融合させる。そうして初めて、一過性ではない、長く地域に生き続ける価値が生まれるのだと。

ジンジャーエールと、お盆の煮物
夜は、買ってきた生姜を使い、ジンジャーエール作り。以前スパイスカレー作りに挑戦した経験が、ここでも活きてきます。スパイスの香りを想像しながら、自分なりの配合を試す。美味しくできているといいな。
お盆らしい、心のこもった煮物をいただき、一日中火照った身体を冷やすため、海風を浴びに散歩へ。
寄り道だらけで、往復35キロ近くを自転車で走り回った身体の心地よい疲労とは裏腹に、心はどこまでも深い学びに満たされた、本当に良い一日でした。

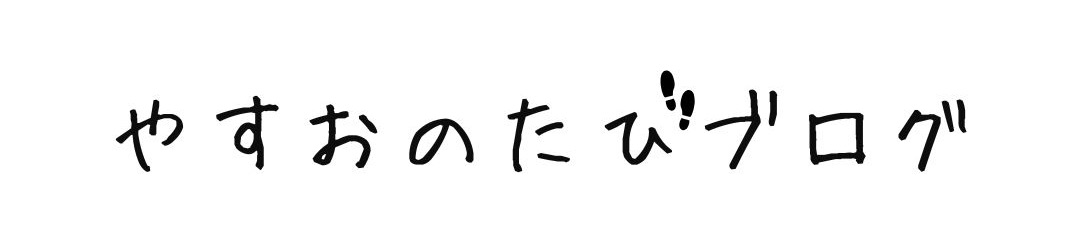

コメント