大雨の音で目が覚めた朝。畑の葉が萎れ始めていた近頃、この雨はまさに「恵みの雨」でした。
午前中はサイトのインデックス対応などPC作業に集中。手探りだったウェブ周りの作業も、少しずつ肌感覚が掴めてきて、純粋に楽しいと感じます。
昼食は九州のファミレス「ジョイフル」でごぼうの唐揚げを初体験し、午後は八代工業高校へ。株式会社イノPの稲葉さんが行う、狩猟に関する講義に帯同させていただきました。
雉を放ち、猪を討つ。生態系における、矛盾した人間の役割
講義の前、私たちはまず、日本の国鳥である「雉(きじ)」を自然に返す「放鳥」を行いました。地域の生態系のバランスを豊かにするための、生命を「増やす」活動です。
しかし、その直後に行われた講義のテーマは、増えすぎた「猪」という生命を、いかにして「減らす」かという話でした。
農業を守るため、生態系のバランスを調整する。その矛盾をはらんだ、人間の難しい役割を象徴するような始まりでした。

知識は、命を守るための盾となる
稲葉さんの講義を初めて拝聴し、事故を起こさないための「正しい知識」の重要性を痛感しました。
捕獲した猪が暴れることを想定し、括り罠は人気のない場所に設置すること。感電事故を防ぐため、電気止め挿し機には二つのスイッチと警告音が備わっていること。
一つひとつのルールが、いかに多くの過去の失敗と教訓の上に成り立っているかを学びました。

銃の重さと、その責任の重さ
講義後、入り口が塞がれた本物の猟銃に、初めて触れさせていただきました。
想像を遥かに超える、その重さ。
これを担いで山中を歩き、狙いを定めることが、どれほど至難の業か。ましてや、猟友会の高齢化は進んでいます。
ふと、思いました。この物理的な銃の重さは、そのまま、命を奪うという行為の「責任の重さ」なのではないか、と。
畑は荒らされ、誰かがやらねばならない。しかし、その責任はあまりに重い。
だからこそ、この仕事の必要性と、その裏側にある覚悟を、若い世代に伝えていく活動は、本当に価値があるのだと感じます。
恵みの雨に始まり、雉を放ち、猪の話を聞く。 農業が、常に自然と共にあるからこその、その複雑さと尊さを、改めて体感した一日でした。


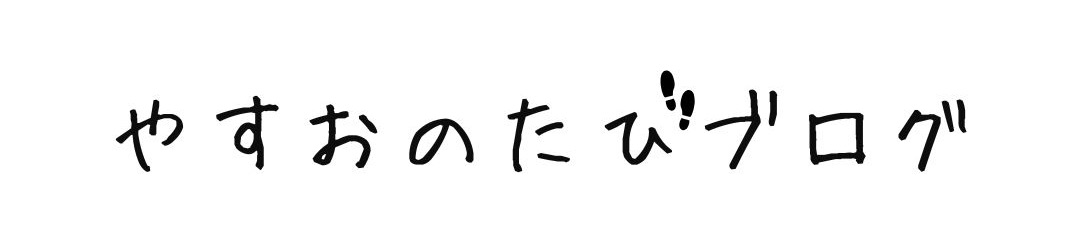

コメント