午前中は宮川洋蘭での作業、夕方からは熊本市内で開催された、ルダシングワ真美さん・ガデラさんご夫妻のトークイベントに参加しました。そのお話は、遠いアフリカの一国の話ではなく、まさに今の日本、そして私自身に突きつけられた、重要な問いそのものでした。

悲劇から「学ぶ」ことで、良い国になったルワンダ
ルワンダで、かつて悲惨な虐殺があったことは、歴史的な事実です。しかし、真美さんはおっしゃいました。「問題があったからこそ、今のルワンダは良い国になった」と。
その言葉は、私が旅人として訪れた時の記憶と、完全に一致します。他の東アフリカの国々では、私は時に「中国人」「ムズング」という記号で呼ばれました。しかし、ルワンダでは違った。誰もが、まず「あなた」という一個人に興味を持ち、「どこから来たの?」と問いかけてくれたのです。
彼らは、民族というラベルで人々が分断され、殺し合った悲劇から、目をそらさなかった。その壮絶な過去から「学ぶ」ことで、個人を尊重する、今の国の品格を築き上げたのです。

なぜ、世界は過去から学べないのか
しかし、世界に目を向ければ、ウクライナ、パレスチナ、コンゴ…かつてのルワンダと同じように、暴力が吹き荒れる場所が後を絶ちません。それは、彼らが過去から学んでいないからです。一度暴力が始まってしまえば、もう遅い。人の命以上に大切なものなど、何一つないのですから。
「対岸の火事」ではない。日本だって、いつ同じような状況になるか分からない。「明日は我が身」です。物理的に紛争から「距離」がある、平和な今の日本だからこそ、私たちはこの問題を真剣に考える必要があります。

距離を凝縮し、未来への架け橋となる
ルワンダの悲劇と、そこからの奇跡的な復興の物語。この強烈なケーススタディは、私たちが「問題が起きる前に、良い国へ」と進むための、最高の教科書です。
しかし、多くの日本人にとって、その教科書はあまりに遠く、リアリティがない。その学びの価値を知らない人が、あまりにも多い。これは、非常に危険な状況です。だからこそ、物理的、そして心理的な「距離の凝縮」が、今、必要とされています。
ルダシングワ夫妻が、28年間という途方もない時間をかけて続けてこられた活動は、まさにこの「距離を凝縮する」ための闘いでした。なぜ続けられたのか。「お金ではなく、『目的』が先にあったからです」とガデラさんは語ります。
私の協力隊としての活動も、この「距離」を少しでも近づける一助になりたい。
もちろん、私が赴任するのはケニアであり、ルワンダではありません。しかし、国は違えど、アフリカという大きな文脈の中で、彼らがその身をもって世界に示してくれた壮絶な学びは、必ずやケニアの未来を考える上での、そして日本の未来を考える上での、重要な示唆を与えてくれるはずです。
その学びの架け橋となるべく、これからの活動を頑張りたい。
お二人の話を聞き、その覚悟に触れ、自分のやるべきことが、また一つ明確になった。そんな一日でした。

▼ルダシングワさんの活動のWebページ
▼過去に私がルワンダ虐殺について書いたnote記事


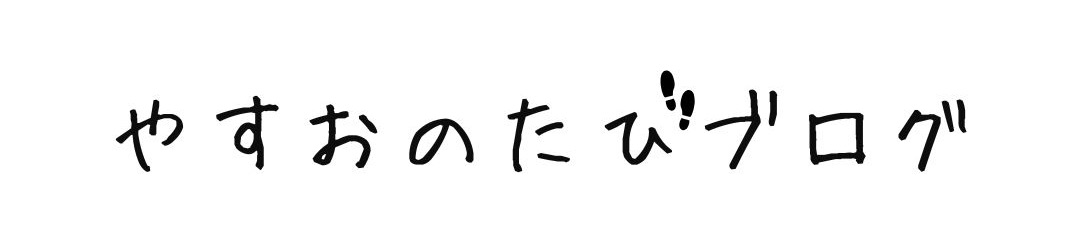

コメント