今日の仕事は、一日を通して胡蝶蘭を曲げる作業。ひたすらに続く、変わり映えのない、超作業。
こうした仕事の中に、楽しさを見出すのは、正直に言って難しいことです。
資本主義の外側で、働くということ
その上、この労働に対して、直接的な金銭の対価が支払われているわけではない。
ふと、自問自答が始まります。
「一体、なんのために、私はこんなにも一生懸命に働いているのだろうか」と。
インセンティブが明確でない労働に、人は情熱を注ぎ続けられるのか。かつて社会主義が崩壊した理由の一端に、ここで触れているような気がしました。
それでも、私の手は止まらない。
この尽きることのない労働意欲の源泉には、一体何があるのだろう。
受け入れ先の方々への「感謝」か、その生き方への「リスペクト」か、あるいはその先にある「野望」のためか。
それは「搾取」か、それとも「投資」か
この状況を、ある人は「感情や、やりがいの搾取だ」と呼ぶかもしれません。
客観的な事実だけを切り取れば、そう見える側面も確かにあるでしょう。
しかし、不思議なことに、今の私は決して不幸ではない。
むしろ、充実していて、楽しいとさえ感じている。この感情は、一体何なのでしょうか。
おそらく、これは単純な「労働」と「対価」の交換ではないのです。
私は、自らの「労働力」という資本を投下することで、お金ではない、しかし極めて価値の高いリターンを得ている。
それは、この場所でしか得られない「知識」と「経験」であり、地域社会や人々との「信頼」という名の社会資本であり、そして、ケニアでの活動へと繋がる「未来への可能性」です。
つまり、これは「搾取」なのではなく、自らの意志で行う、未来への「自己投資」。
だからこそ、そこに喜びと楽しさを見出すことができる。今は、そう考えています。
指導者の苦悩と、「伝える」ことの面白さ
夜は、少年団サッカーの練習へ。
特に前半、子どもたちの雰囲気はどこか、ふわふわしている。集中力を欠いたその光景を見て、かつて自分が指導者から怒鳴られていた理由の一端が、少しだけ分かった気がしました。
もちろん、感情を剥き出しにすることが良いとは思いません。しかし、人の心を一つの方向へ導くことの難しさ、指導者という立場の苦労にも、ほんの少し触れられた気がします。大変な仕事です。しかし、だからこそ、面白い。
来週もまた、いかにして彼らに「伝える」か、試行錯誤を続けようと思います。

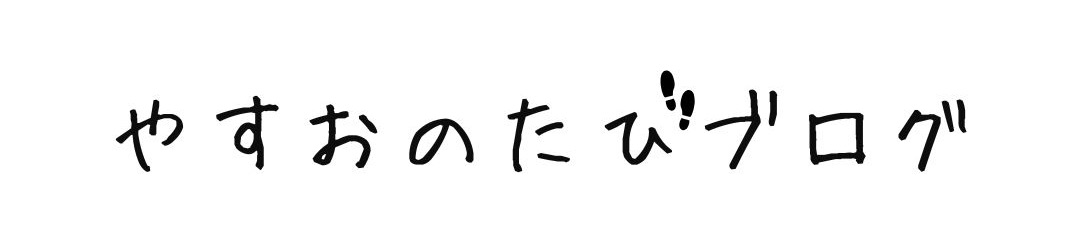

コメント