朝、胡蝶蘭の鉢を移動させる作業から、一日が始まりました。
午前10時からは、グローカルプログラムに参加する全国の同期たちがオンラインで一堂に会す、全体のミーティング。グループワークで、それぞれの活動の進捗や学び、うまくいっていること、そして悩みを共有しました。
多様なアプローチの中に、共通点を見出す
受け入れ先も活動内容も、本当に様々。普段はそれぞれの場所で奮闘している仲間たちの話は、どれも新鮮で、学びの連続です。
そして、そんな多様な経験の中に、ふと「あ、その悩みは自分も感じていた」と、共通の課題が見つかる瞬間がある。これが、非常に面白い。
さらに興味深かったのは、「課題とソリューションは一対ではない」という事実です。
例えば、時として共通する「地域の方々とのコミュニケーションが、なかなか深まらない」という課題一つをとっても、その解決策は十人十色。
ある人はイベントを企画し、ある人はひたすら一対一の対話を重ねる。それぞれの置かれた文脈の中で、誰もが自分なりのアイデアで、その課題と向き合い、実践している。その多様なアプローチに触れられたことは、非常に大きな学びでした。
試される「ファシリ力」と、嬉しいフィードバック
今回のグループワークで、私は受け入れ先から課題としていただいている「ファシリテーション能力」を意識して臨みました。話が円滑に進むよう、問いを投げかけ、議論を整理する。その中で、他の研修生から「なんか、コミュニケーション能力ついたね」という言葉をかけてもらえました。ささやかな一言ですが、自分の成長を客観的に伝えてもらえたようで、本当に嬉しかった。もっともっと、頑張りたいと、強く思います。
竹を切り、スイカをもらう、という対話
午後は、仕事の合間に、毎日通う宮川洋蘭への道のりの写真を撮りに出かけたり。 仕事の後には、ご近所の方のお手伝いで、家の近くの竹を刈ったり。すると、お礼にと大きなスイカをいただきました。
言葉を交わすだけが、コミュニケーションではない。写真を撮ってその土地の魅力を伝えることも、労働力を提供してスイカをいただくことも、この地域との豊かで、温かい対話なのだと感じます。

夜は、月曜日に行えなかった分の勉強会。
全国の仲間とのオンラインでの対話、個人的なスキルの実践、そして地域での温かい交流。今日は一日を通して、多様な「コミュニケーション」の形とその重要性について、深く学んだ気がします。

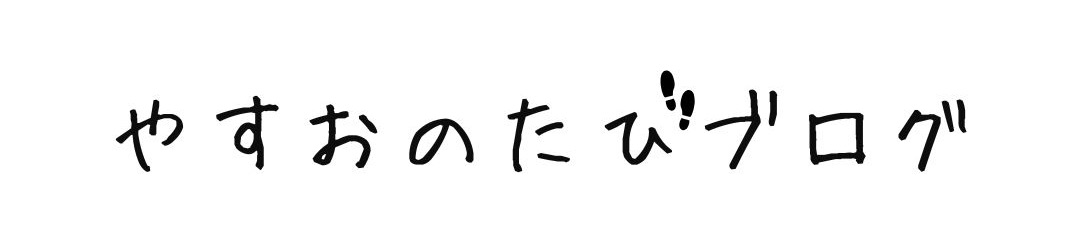

コメント