今日の仕事は、初めて「グラスブーケ」の作業に携わらせていただきました。
特殊な加工で花の美しさを長持ちさせる、この人気商品。私が担当したのはグラスを磨き、梱包する最終工程の一部でしたが、この研修に参加した大きな理由の一つである「第六次産業」の現場を、ついに垣間見ることができました。
生産、加工、流通。すべてを担うことの、途方もない難しさ
そして、そこに広がっていたのは、想像以上に険しい道のりでした。 「第六次産業化」という言葉の響きは華やかですが、その裏側にあるオペレーションは、想像を絶する複雑さと困難さを内包しているのだと痛感します。
- ①生産:まず、種や苗から、天候と闘いながら高品質な作物を安定的に育てる。
- ②加工:次に、その作物の価値を最大化するため、特殊な設備を導入し、鮮度を保ちながら付加価値の高い商品へと加工する。
- ③流通・販売:そして、その商品を最も良い形でお客様に届けるため、ブランドを構築し(マーケティング)、ECサイトや直販所といった販路を開拓し、在庫を管理し、受注・梱包・発送を行う。
これら、性質の全く異なる専門領域の全てを一つの組織で担うことが、いかに難しいか。それは到底一人で回せるものではなく、各部門の品質を担保するための人材育成や、巧みな権限委譲といった、高度な経営手腕が求められます。一般的な家族経営の農家が、この高いハードルを越えるのは、極めて困難な挑戦でしょう。

日本の農業が抱える、構造的な課題
では、そもそも「生産」の規模を拡大すれば良いのかというと、それもまた簡単ではありません。
日本の農地の多くは、区画整備されていない中山間地域に点在し、土地への愛着から売却を望まない所有者も多い。農地を集約し、大規模化すること自体が、まず一つの大きな壁として存在します。
生産規模の拡大も、第六次産業化による高付加価値化も、それぞれに高い壁がある。
今、私は、日本の農業”経営”が直面する構造的な難しさを、身をもって体感しています。
答えは、実践の中に。
だからこそ、先日来学んでいる農家ハンター(イノP)のようなアプローチに、大きな可能性を感じるのかもしれません。
一つの組織が全てを担う「垂直統合」ではなく、地域内の多様なプレイヤーが連携する「水平連携」。
それぞれが自立しながらも、緩やかに繋がる「自立分散型のエコシステム」をどう構築していくか。
机上の空論で終わらせないためには、何が必要なのか。
おそらく、その問いに対する唯一絶対の答えはありません。
だからこそ、これから始まる青年海外協力隊としての2年間、そしてこの残りの研修期間で、実践を通してその答えを模索していきたい。
それが、今の私の目標です。
ただ、最近、あれもこれもと挑戦しようとしすぎて、少し空回りしている感覚がありました。
心に余裕がなくなり、新しい知識をインプーットする時間も取れていない。
それは、今の自分にとって一つの大きな課題です。
壮大な目標を前に、まずは、一旦、深呼吸。
自分の立ち位置を冷静に見つめ直し、今やるべきことに、また明日から集中しようと思います。

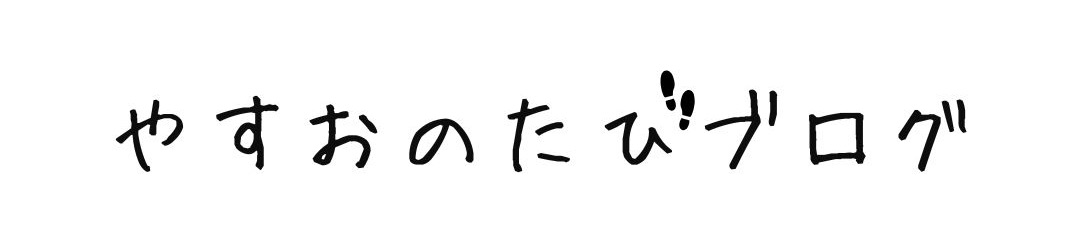

コメント