今日の仕事は、一日を通して小さな蘭の花を曲げる作業。大きな胡蝶蘭とはまた違う、繊細な難しさがあります。僅かな力加減の誤りで、愛らしい花がぽろりと取れてしまう。その儚さに、改めて生命を扱うことの緊張感を覚えました。
なぜ、私たちは簡単にモノを捨ててしまうのか
そんな繊細な作業の傍ら、耳では芸人でありながらゴミ清掃員としても働く、マシンガンズ滝沢さんのポッドキャストを聴いていました。テーマは「ゴミについて」。
「顔が見えないことが、ゴミをゴミたらしめている」
例えば、安いからという理由で買った百均の雑貨やファストファッション。「一枚買うともう一枚無料」でついてきた、結局食べきれないピザ。私たちは、その作り手の顔や、捨てられた後のコストについて深く考えません。顔が見えないから、簡単に買い、そして簡単に捨ててしまうのです。
ゴミの分別のルールを守らない人がいるのは、それを回収する清掃員の顔や、最終処分場の姿を知らないから。周りの目がないから、私たちは平気でゴミを出す。
彼の知人は、彼がゴミ清掃員であることを知ってから、ゴミの分別を丁寧にし始めたそうです。作り手、運び手、そして処理をする人。その全ての連鎖の中に「顔」が見えた時、モノは、単なる「ゴミ」ではなくなるのです。

見えないものに想いを馳せる、ということ
この話は、私が今向き合っている仕事とも深く繋がります。一輪一輪の花を大切に扱うのは、その先に待つお客さんの「顔」を、そして何より、ここまで育ててきた生産者の「顔」を知っているからです。
見えないもの、遠い場所に想いを馳せる。
その想像力こそが、現代社会で失われがちな、しかし最も尊い「豊かさ」の本質なのかもしれない。
そんなことを、蘭の花をそっと曲げながら考えていました。
加速する時間と、やるべきこと
最近、時間の流れが加速度的に速くなっています。
今週は、戸馳島での「車座(宮川洋蘭・イノP関係者の方々との対話の場)」の企画や、直販スペースの改良、そしてCRM構築に向けた要件定義など、思考を巡らせるべきタスクが山積みです。
見えない価値を、どうすれば見えるようにできるか。
一つひとつのタスクに、今日の学びを活かしていこうと思います。

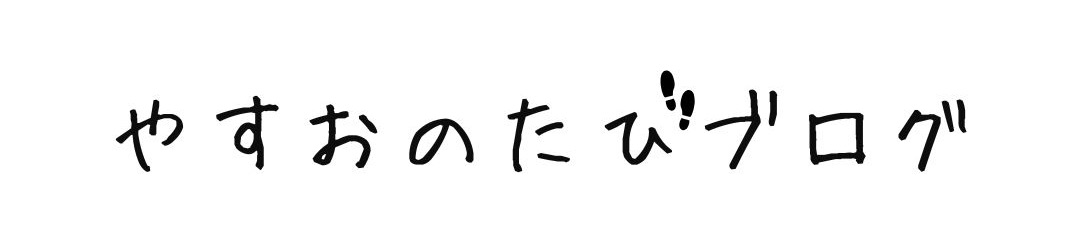

コメント