週初めの月曜日。朝礼での社長のお話は、また何か新しいことが始まる予感をさせる、ワクワクするものでした。今週も頑張ろう、と気持ちが引き締まります。
午前中は、ひたすらブルーベリーの剪定作業。鋏を握り続けた右手の握力は、いよいよ弱くなってきました。その傍ら、耳からは農業経営に関する本をインプット。毎日2冊ほどの知識を浴びるように吸収していますが、それを単なる”消費”で終わらせないよう、常に自問自答を続けています。
プレゼンの常識が通用しない、出前授業という挑戦
午後は、宇城市の青海小学校へ。5、6年生を対象とした出前授業の本番です。 この授業は、想像を遥かに超える難しさでした。大人に話すことよりも、ずっと。自分なりに準備してきたつもりでしたが、今思えば、その準備は全く足りていませんでした。
どうすれば子どもたちを飽きさせず、しかし、本当に伝えたいことはどう届けるのか。その絶妙なバランスは、”相手の目線に立った”徹底的な準備なしには成り立ちません。言葉選び一つ、スライドの見せ方一つにも、特別な配慮が必要です。
これまで私が資料を作ってきたのは、印刷物か、個々のPC画面で見るオンラインの世界。しかし、教室という物理的な空間では、「後ろの席の子までモニターの文字が見やすいか」「私の声は、一番後ろまで届いているか」といった、当たり前で、しかし決定的に重要な配慮が求められます。
慣れた環境で大量の資料を作れてしまうという、これまでの経験の「功罪」に気づかされた瞬間でした。その時、その場所、その人たちにとっての最適解をデザインすること。あらゆるプレゼンテーションに通じる、本質的な学びを得ることができました。

恩送りの連鎖と、一期一会の出会い
学校から戻ると、宮川洋蘭に宮川さんを訪ねてきた方がいらっしゃいました。人生相談のために、来られたとのこと。お話を伺うと、かつて宮川さんが、その方のお父様にお世話になっていた、という背景がありました。
受けた恩を、次の世代へ、別の誰かへ。この美しい「恩送り」の連鎖と、人と人との繋がり。私も、こうした一期一会の出会いを、心から大切にしていきたい。そう強く思いました。
夜は、週に一度の勉強会。今日は出前授業でたくさん声を使ったので、久しぶりに喉が疲れましたが、定期的なアウトプットの機会は、やはり自分のためにもなります。 人との関わりの中で、多くのことを学んだ一日でした。

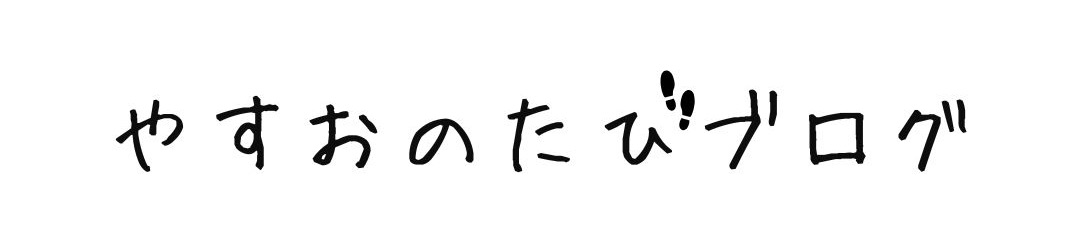

コメント