JICA九州でのオリエンテーション最終日。
今朝は少しゆっくりと、仲間たちと会話をしながらビュッフェ形式の朝食をいただきました。
しっかりとした朝食は、心と体にエネルギーを満たしてくれます。

「よそ者」として、どう価値を発揮するか
本日の研修は朝9時から夕方6時まで。
昨日のJICA組織に関するマクロな話から一転し、今日はグローカルプログラムに焦点を当てた、より実践的な活動計画の立て方や「地域創生」に関する講義がメインでした。
特に、大学教授を招いて行われた地域創生の講義は白熱しました。
次々と手が挙がり、予定時間を大幅にオーバーするほどの質疑応答。研修生たちの関心の高さを肌で感じ、私自身も大きな刺激を受けました。
今日の講義を通して、深く考えさせられたテーマは「”よそ者”としての自分をどう捉えるか」でした。
地域に飛び込む私たちが陥りがちなのは、外からの目線で一方的に課題を見つけ、解決しようとすること。しかし、大前提として「住民は、課題の中に生活しているわけではない」。彼らの日常や文化を無視して、よそ者が好き勝手に何かをやっても、想いが届くはずがありません。
では、どうすべきか。
私が今、考えているのは、「よそ者」だからこそ「異物」としての価値がある、ということです。
まずは現地の生活に敬意を払い、対話の中で彼らが大切にしているものを感じる。その上で、異物である私という存在が、良い意味での化学反応を起こす「エッセンス」として、地域にどんな新しい風を吹き込めるのか。それが私の役割なのだと、考えが整理されました。
夢を語り合う、心地よい夜
夜は、九州に派遣されるメンバーとささやかな飲み会へ。
改めて感じたのは、「やっぱり、みんな変だ」ということ。
良い意味で、社会のレールから少しはみ出した人たちの集まり。
それが最高に面白い。
年齢も経歴もバラバラな人間が、一つのテーブルを囲んで、それぞれの夢や、この社会に対する自分なりのテーゼを熱く語り合う。
もちろん、話の中では互いの考えに違和感を覚えたり、言葉の「誤植」が生まれたりもします。
でも、そのズレや違いこそが、この場の面白さを加速させていました。
たった3日間とは思えないほどの密度の濃い時間を共にし、確かな仲間意識が芽生えていました。
それはきっと、皆がどこか「外れている」という共通項を持ち、年齢や性別に関係なく、互いの夢をリスペクトし合える関係だから。
とても心地の良い空間でした。
別れるのが寂しいです。

JICA九州でのオリエンテーションは、今日で終わりです。
いよいよ明日、私は活動地である熊本県、戸馳島へ向かいます。
さて、頑張ろう。

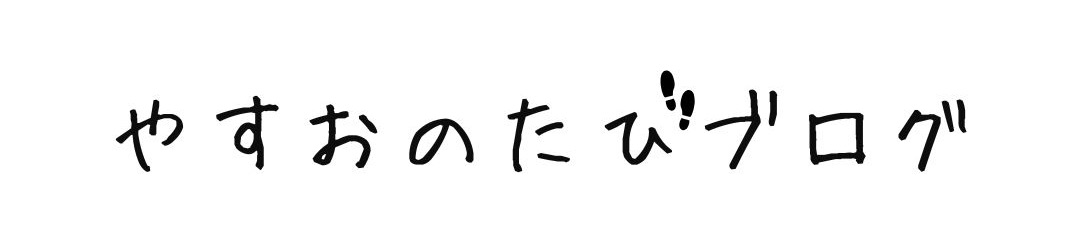

コメント