涼しい風が吹いた今日、久しぶりに一日中いちごのハウスの片付け作業に専念しました。長かったこの作業も、ついに今日で終了。一つの旅を終えたような、清々しい達成感があります。
そして、一つの終わりは、新たな始まり。早速、ブルーベリーの剪定方法を教えていただきました。

九州の剪定、北海道の剪定
ブルーベリーの剪定は、想像以上に奥が深く、面白い世界でした。新しい単語の多さに少し混乱しかけましたが、それ以上に驚いたのは、素人目には心配になるほど、大胆に枝を切り落とすこと。想像の3倍は剪定している感覚です。
しかし、これには明確な理由がありました。九州の気候は成長スピードが速く(東京を1とすると約1.7倍)、このくらい強く剪定しても、すぐに新しい芽が力強く生えてくる。一方で、成長が緩やかな北海道(約0.7倍)では、同じやり方は通用しないそうです。
場所が違えば最適な方法は異なり、毎年変わる気候の中でその最適解を探し続ける。農業とは、まさに「終わりなき探求」なのだと実感します。

なぜ多くの農家は「農協」を選ぶのか
この「終わりなき探求」という現実は、作業をしながらAudibleで聴いていた『金持ち農家、貧乏農家』や『直販・通販で稼ぐ! 年商1億円農家』といった本の内容とも、深くリンクしました。
農業というビジネスは、生産能力と製品クオリティという土台の上にしか成り立ちません。そして、その土台を築き、維持すること自体が、極めて難しい。特に新規就農であれば、時間も体力も、その全てを生産に全投下しなければならないほどです。
そう考えると、多くの農家が「農協(JA)」に出荷する、という選択がいかに合理的であるかが理解できます。生産という専門領域に集中するために、経営や流通という、これまた片手間ではできない仕事を外部に委託する。それは、非常に理にかなった経営判断なのです。
「正解」がないからこそ、価値がある
一方で、私が今お世話になっている宮川洋蘭は、巧みな権限委譲によって生産と経営の絶妙なバランスを取り、D2Cモデルを確立しています。これもまた、一つの正解の形です。
本で紹介されていた数々のケーススタディに、絶対的な一貫性はありませんでした。それは、農業生産に唯一の正解がないのと同じです。その土地、その気候、その年の状況によって正解は常に変わる。そして、農業経営にもまた、誰もが真似できる万能のメソッドは存在しないのです。
結局のところ、本や人から原則を学びつつも、最後は自分自身で考え、試し、その手でスキルを掴み取るしかない。
この研修中に宮川洋蘭の社長からたくさんのものを吸収しようと、覚悟をあらた覚悟を新たにさせてくれました。

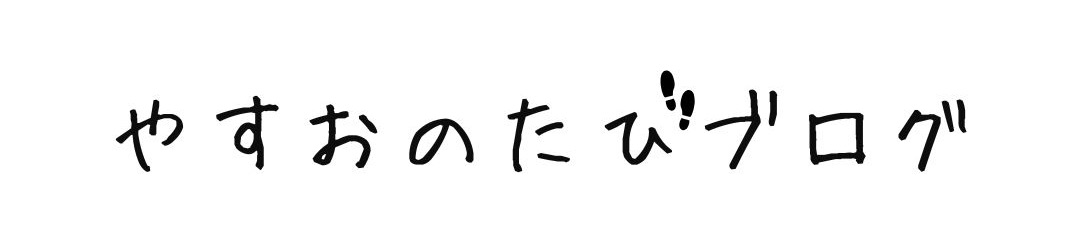

コメント