気づけば、戸馳島に来てから2週間。体感としてはあっという間でしたが、一日一日を振り返ると、たくさんの刺激的な出会いや出来事があり、とても長かったようにも感じます。目の前のことに、がむしゃらに突っ走ってきたからかもしれません。
今日も午前中はブルーベリーハウスの片付け。相変わらずの暑さです。 ただ、その合間に1時間ほど、株式会社イノPを訪ねてこられた方への説明に同席させていただきました。
捕獲の”その後”ー捨てられるイノシシという現実
その方は、イノシシの堆肥をより使いやすくするため、成分の研究目的で来訪されていました。そのお話の中で、私は獣害問題の、また一つ根深い課題を知ることになります。
現在、捕獲されたイノシシのほとんどは、適切に利用されることなく”捨てられている”という事実。ルール上は埋葬義務がありますが、実情は土を軽く被せるだけで、結局は他の動物の餌となり、鳥獣被害を削減するどころか、かえって加速させている可能性さえあるのです。
イノPでは、この現状に対し、肉質が良いものはジビエ肉に、それ以外は堆肥へと加工する取り組みをされています。「捕獲→止めさし→処理→利用」という一連の流れの中で、以前「捕獲」と「止めさし」の難しさに触れましたが、この「処理」と「利用」もまた、想像以上に大きな問題でした。
宇城市で年間1000頭、天草では1万頭。そのうちジビエにできるのは、ほんの一握り。そのジビエ事業でさえ、黒字化は非常に困難です。堆肥化するための機械は超高額で、行政の規制も厳しい。ビジネスとしての見返りが、現状ではあまりに少ないのです。

課題の山から生まれる「金の卵」
しかし、イノPの稲葉さんは、この厄介者のイノシシを「金の卵」だとおっしゃいます。
今はまだ多くの障壁がありますが、栄養豊富な有機物であるイノシシは、堆肥以外にも様々な可能性を秘めている。もし、社会起業家たちのもとへ資金が集まるような社会システムが生まれ、この課題解決のために地方へ人が集まるようになれば、この状況は一変するかもしれない。日本の生態系を揺るがす大きな問題が、社会に莫大なインパクトを与える「金の卵」に変わる可能性があるのです。
道のりは長いですが、生態系の変化は待ったなしです。この2ヶ月という恵まれた環境の中で、私に何ができるのか、模索を続けたいと思います。

屋根の上と、迫りくる中間発表
午後は、宮川洋蘭で胡蝶蘭の出荷作業を手伝い、16時からはハウスに日除けシートをかけるため屋根の上へ。遮るもののない屋根の上は、夕方とはいえ強烈な暑さでしたが、高い場所からの眺めに少しだけ興奮しました。

夜は、九州チームとの週次ミーティング。中間発表の予定も決まり、いよいよ最終発表に向けて本格的に動かねば、と気持ちが引き締まります。目の前の仕事に精一杯なのは皆同じで、発表準備との両立に、仲間たちも頭を抱えていました。
まずは、目の前のことから一つずつ。
夜ご飯は、いただいた鰻で英気を養いました。
明日からも頑張ります。


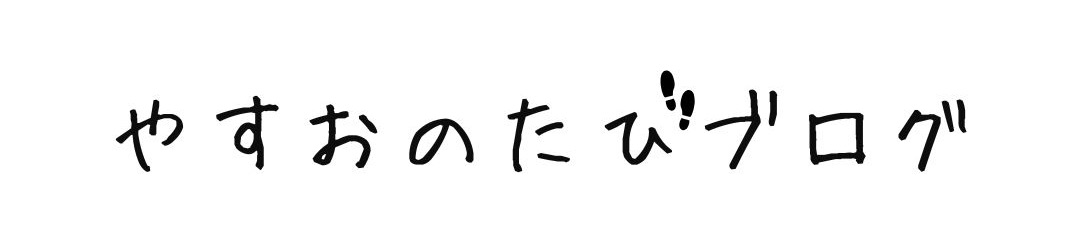

コメント